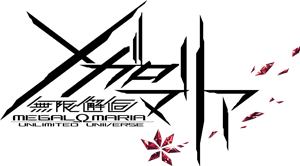その一言は、まるで舞台脚本に書かれた台詞のようだった。
「プリンシパル、と申します。どうぞ、終演までお付き合いくださいな」
篝火真里亞から現れた女性型アナザーが、軽やかに着地しながらそう名乗る。隣の真里亞が怒りを隠さずにいるのとは対照的に、その口ぶりは不気味なほど柔和だった。
「……まさか」と、昇藤駿が言う。「口説こうとした子が、トリガーだったとはね」
「口説く? 心を壊して怪人にする、の間違いでしょう」
「全部分かってるのか。俺を炙り出すのが狙いだったわけだ」
面白くないな、と吐き捨てて、駿は並び立つ人間 と怪人 を見た。
本来、人間とアナザーは共存不可能な関係にある。人間に寄生したアナザーは宿主の負の感情を餌にして育ち、やがて宿主を喰らい、成り代わる。それはある意味で、深い絶望に苛まれ続けてきた宿主にとっての救いでもあるがゆえに――多くの人間は、抵抗もできずに体を明け渡してしまう。
だが、ごく稀に――その絶望を超克し、内なる怪人 を己が力とする者が現れる。
トリガー。
この世界の黄昏――人間の怪人化に対抗しうる、唯一の存在。
「……さすがに、何もせずに逃げ帰るわけにはいかないか」
そう呟いて、駿は主の命令を待っている彼女 に短く呼びかけた。
「エリカ、殺れ」
と、まるで機械のスイッチが入ったかのように動き出したエリカ・アナザーが、真里亞に鎌を振るう。予備動作のほとんどないその斬撃は――しかし、割って入ったプリンシパルに容易く受け止められた。
「……言いつけ通りにしか動けないなんて、所詮は量産型 ですわね」
主演女優 が、失望の目でエリカ・アナザーを見る。
格が違う。
本能でそれを感じたのか、エリカ・アナザーは戸惑ったように身震いし、プリンシパルを振り払って距離を取る。そして、仮面の三つ目が妖しく光らせて唸り声をあげると――その右の手首を、ありえない角度に折り曲げていった。
「グ、ギ……。ガガガガガァッ!!」
痛みを堪えるかのような絶叫と共に、エリカ・アナザーの右手首が折れる。と、それまで逆刃についていた手首の刃が前方に突き出て――カマキリに似た、腕と一体の鎌となった。
「ガ、ガ……」
ゆらり、と不気味な前傾姿勢を取って、エリカ・アナザーが二人を見る。
「真里亞ちゃん、下がってて」
進み出たのは、プリンシパルだった。
「……どうして?」
「知り合いなんでしょう? そんな子と真里亞ちゃんを戦わせたくないもの」
「……」
短く溜息をついて、真里亞が刀を引く。
瞬間――エリカ・アナザーが、二人を目掛けて跳びかかってきた。
脱力していたはずの前傾姿勢から、動物的な跳躍。本能のままに、ゆえに凄まじい速度で振り下ろされた二刀の鎌を、プリンシパルは軽やかに退がって躱す。
踊るような、そして優美な動き。
エリカ・アナザーが交互に鎌を振るえば体を半身に傾けて避け、横薙ぎに斬りかかれば上半身を反らして倒立し、大振りとみるや相手の腕を支点にして空中で側転する。あたかも予定調和の殺陣のように、プリンシパルはエリカ・アナザーのことごとくを回避していった。
「ああ、気の毒に……。その体での動き方に慣れていないのですわね」
「ギィアァッ!!」
哀れむようなプリンシパルの言葉を挑発と受け取ったのか、エリカ・アナザーが渾身の力を籠めて右の鎌を振り下ろす。
と――プリンシパルは片足を引いてそれを躱し、エリカ・アナザーの右腕に体を沿わせてくるりと一回転 すると、逆手に持った短刀――「イシュタム」を、エリカ・アナザーの仮面に突き立てた。

「ガ、グ……!?」
雷に打たれたように、エリカ・アナザーの体が硬直する。プリンシパルがそのまま腕を振り抜き、「仮面」を上下に両断すると――その下から、“時園エリカ”の顔が現れた。
「……第一幕は、これでおしまい」
エリカ・アナザーが鎌を取り落とし、乾いた金属音が響く。
全身の力が抜けて崩れ落ちかけた彼女を、プリンシパルが優しく受け止める。気を失っている“時園エリカ”の首筋は怪人 の外装に変質しかけており、身も心もアナザーに乗っ取られる寸前であったことが窺えた。
その外装がボロボロと崩れ、「人間」のそれに戻っていく。
「お帰りなさい。時園エリカさん」
プリンシパルは彼女をそっと地面に横たえて、慈しむようにその頬を撫でた。
■
「……あれが、“開花”したアナザーの力か」
その路地裏から少し離れた高層ビルの屋上で、昇藤駿は思わずそう零した。
人間の心を壊すことで産まれるアナザーとは何もかもが違う。心を壊したがゆえに命令に従うことしかできない量産型 がまともに戦える相手でないことは明らかだった。
「一回でも殺しを経験してれば動きも違うんだが……ま、“未完成品”ならあんなもんか」
軽い口調で言って、駿はその路地裏に背を向ける。
エリカ・アナザーが気を引いてくれたおかげで、労せずして戦線を離脱することができた。自らの狩場である“Spider”でトリガーに出くわしたのは想定外だが、見たところ、彼女たちはいずれの組織にも属さない「野良の」トリガーである。この場さえ逃れることができれば、駿を再び見つける手段はないだろう。
「もう少しあの子たちのデータが欲しいところだけど、それは俺の仕事じゃないな。さっさと教団に報告して……ああ、アカウントも転生しないと」
小声で呟きながら指を鳴らすと、空間が歪み、彼の“研究室”へと繋がる転送円が開く。
駿がその内側に身を滑り込ませようとした、その時だった。
「――見つけた」
刺すような殺意を感じて、駿は振り向く。
ゆうに10メートル以上は離れている、隣のビルの屋上。その欄干を踏みしめ、黒き長髪をたなびかせていた少女が――弾丸のごとく、彼めがけて跳躍した。
「うっ!?」
否、狙いは彼ではなかった。空中で刀を引き抜いた少女は、咄嗟に飛び退いた駿には目もくれず、転送円を袈裟斬りに破壊する。
「プリンシパル!」
「ええ」
そして――死角から飛来した短刀 が、彼の右足甲を刺し貫いた。
「ぐあっ!」
短刀は屋上の床に深々と突き刺さり、駿の動きを封じる。激痛に膝を、そして手をついた彼の目に映ったのは、先ほどまで路地裏にいたはずのプリンシパルの姿だった。
「卑怯なのね。時園さんを矢面に立たせて逃げるなんて」
顔を上げると、篝火真里亞が駿を見下ろしている。
「……ああ、そうだった」と、駿は苦い顔をして言う。「“開花”すると、トリガー自身の身体能力も強化されるんだったね」
「あなたには聞きたいことが山ほどある。逃がしはしないわ」
「……」
駿を脅しているつもりなのか、真里亞は駿の喉元に刀を突きつけてくる。その刃先ではなく――間近に迫った真里亞の声に“女”を感じて、駿の体 に寒気が走った。
「まずは他の被害者の情報、それからあなたたちの手口について。単独犯なのか、協力者がいるのか、あるいは……“Spider”そのものが、人間を怪人化させるために開発されたのか」
「相変わらずまっすぐねえ。答えてくれるわけないのに」
呆れたように肩を竦め、プリンシパルは「そういうところが可愛いんだけど♪」と艶やかに笑う。その――ある意味で女性的な――甘ったるい笑い声にも体 が拒否反応を示し、駿は眉を顰めた。
「では、私からもひとつ質問を」
その僅かな身じろぎを見逃さずに、プリンシパルが駿の顔を覗き込む。
「貴男が乗っ取った 人間。元々の宿主は、女性が苦手だったのではないですか?」
それは――気付いている者の問い方だった。
「……何の話だ?」
軽薄を貫いてきた駿の言葉に、敵意が混じる。
プリンシパルはくすりと笑って、「失礼。いささか直截でしたわね」と慇懃に言った。
「貴男の“体の”反応を見れば、女性に苦手意識を抱いているのは明らかです。一方で、貴男はその女性を口説き落として怪人にしている。何故ですか?」
「効率の問題だよ。思春期の女の子は精神的に不安定だから、心を壊しやすいしね」
「そんな理由で……!」
突きつけた刀に力を籠めようとした真里亞を、プリンシパルが制する。
「そう。貴男の“心”は、女性を実験台にしか見ていない。まるで――女性を苦手としていた“体”を、全く別人の、人を人とも思わない“心”が乗っ取ったかのように」
芝居めいた調子で長台詞を披露しているにもかかわらず、彼女 の眼差しからは警戒の色が消えない。真里亞も人間相手の手加減があった構えを正し、刀の柄を握り直した。
「……『乗っ取った』?」
薄く開いていた駿の口が、笑みの形に変わる。
「人聞きが悪いなあ。その言い方じゃ、まるで俺がそこらの量産型みたいじゃないか」
そのニヤケ面の奥に宿した敵意を隠さずに、彼は二人を見上げた。
「その通り。この“体”は……『昇藤駿』は、女性恐怖症だった。高校までは大して目立つ男でもなかったのに、医学部に入ったってだけで次々と女に言い寄られてね。女の言葉が本心からのものなのか、それとも打算の産物なの分からなくなったらしい。
そんな『昇藤駿』にとって――研究で発見した量産型 の存在は、まさに福音だったのさ」
未発表に終わった「昇藤駿」の論文には、こう書かれている。
[結論A]「アナザー」は、その発現の仕方によって3つのパターンに分類できる。
[A-1:量産型]人間の心を壊すことで発現。意思を持たない。
[A-2:開花型]トリガーの「開花」によって発現。意思を持つ。
[A-3:黄昏 型]人間が自らの意思で体を譲り渡す ことで発現。意思の有無は不明。
この中で、駿が注目したのは[A-1]のアナザーだった。
「意思がなければ、本音も嘘もない。『全人類が量産型のアナザーになれば、世界はどんなに分かりやすくなるだろう』って、奴はよく言ってたよ」
だが、と、駿は笑う。
「そのためには、お前たち が邪魔だった。だから奴は、お前たちを排除する力を求めて――この“俺”に、体を譲り渡したんだよ」
そう言って、彼 は――地面につけていた片手を、引き抜いた。
「――糸!?」
その指先から五本の“糸”が伸びているのを見た真里亞が息を呑む。手をついた振りをしてコンクリートの内部に張り巡らせていたのだろう。超硬度の“糸”が一斉にのたうち、真里亞とプリンシパルの足元を、崩壊させた。
「なっ……!?」
「っ、真里亞ちゃん!」
遮るもののない空中に放り出された二人が、驚愕の表情で落下していく。駿は目を細めて彼女たちに笑いかけると、その掌に仮面を出現させた。
「仮面……!」
「お前の望みを叶えてやるよ、『駿』。あのトリガーとアナザーは、今ここで屠る」
「貴男、やはり……!」
遠ざかっていくプリンシパルへの返事代わりに――彼 が、仮面を装着する。
「おおおおおおおおおおおおおおおあああ!!」
つんざくような絶叫と共に、「昇藤駿」の体が変質を始める。禍々しき光に包まれた腹が割れ、脚が割れ、人の形を失った下半身からいくつもの足が生えてくる。かろうじて原型を留めていた上半身も黒化し、氷が割れるような音を立てて無機質な外装に包まれてゆく。
――蜘蛛の如き八つ足の下半身と、機械人形のような人型の上半身。
「あれが……彼の本当の姿……!」
階下に着地した真里亞が、殺意と、少しばかりの哀れみを籠めて、その怪物を睨む。
強制的に怪人化したのではない。トリガーとして開花したのでもない。
人間が自らの意思で人を捨て、内なる怪人 に魂を売った成れの果て――冷血なる破壊者 たち。
「――我が名は“ラヴェナス”。この偽りの世界に、黄昏をもたらす者なり」
あまりにも異質なその姿は、「昇藤駿」がもう人間ではないということの証左だった。
■
こんな大人にだけはなりたくないな、と根本ランは考えていた。
「こんだけ痣ができてるんだよ!? 見りゃ分かるでしょ、こっちが被害者なの!」
「分かりましたから、続きは署で……」
「行くわけないだろ! もう帰してくれって言ってんの!」
ランとスミレが連れてきた警官に、エリカを“買った”であろう中年男がまくし立てている。被害を訴える一方で事情聴取は拒むという矛盾した態度からは「この場を逃れたい」という本音が見え透いていて、ランは辟易とそのやり取りを眺めていた。
初めこそ驚きはした。指示通りに警官を呼んできたら真里亞とエリカの姿はなく、 “買い手”だったはずの男が地面に転がって呻いていたのだから。ランとしても何が起きたのか知りたいところだったが、男がひたすらに「大したことないから帰してくれ」と怒鳴り続けるのを聞いているうちに、その好奇心も萎えてしまった。
「はあ……。帰りたいのはこっちだっての」
溜息をつきながら自分のスマホを見る。真里亞宛てのメッセージに反応はない。
「てか、真里亞どこ行ったの? さっさとエリカ連れてきてさ、マッチングアプリのログでも見せれば一発で証拠じゃん。ね、スミレ」
「……」
「スミレ?」
「え? あっ、ごめん……。なに?」
不思議そうに辺りを見回していたスミレに「どしたの?」と首を傾げる。スミレは普段にもまして自信なさげに「え、えっと……。ちょっと疲れちゃったみたいで……」と切り出すと、少し視線を上げて周囲のビルを指差した。
「さっき、あそこのビルがひび割れて、崩れそうになったような気がして……。でも、何度見直しても、何ともないし……」
「あはは。なんじゃそりゃ」
目を擦るスミレを小突いて、ランもぐるりと周囲のビルを見る。
特に異常のない、いつもの街並みだ。ネオンぎらつくホテル群の向こうには、一目で残業中のフロアが分かるオフィスビル、居酒屋の看板が眩しい雑居ビルなど高低様々な建築物が建ち並んでいるが、ヒビの入ったビルなんてものは見当たらない。本人の言うとおり、疲れか何かで見間違えたのだろう。
ランとしても、男の醜い言い訳はこれ以上聞くに堪えない。「今日はもう帰ろっか」と提案しようとした時、スミレがとんでもないことを言い出した。
「そ、そういえば……。エリカちゃんとあの男の人が……その、アレな服を買ってるところなら、動画に撮ってあるけど……」
「は?」
「でも、か、隠し撮りで……。おまわりさんに見せて大丈夫、かな……?」
スミレのスマホを確認する。そこに映っていたのは、いかがわしい服をエリカに買い与える男の姿であった。これ自体を証拠にできるのかどうかはランには分からないが、少なくとも彼が単なる「被害者」ではないことを示すには十分だろう。
「……あのね、スミレ」
「う、うん」
「早く言えっ!」
言うや否や、ランはスマートフォンをひったくった。そして、今までの時間は何だったんだとばかりに大股で警官のもとに向かう。そんな彼女の後ろを、“盗撮犯”――スミレが不安げに追いかけていった。
――その二人の、さらに背後。
そこに建つ一棟の高層マンションに巨大な亀裂が走り――その亀裂がすぐさま消滅したことに、二人は気付かなかった。
■
崩れゆく高層マンションから飛び出した真里亞の目を、「蜘蛛の糸」が貫かんと迫る。
糸と言っても、その強度は鋼鉄よりも高い。真里亞は咄嗟に刀を振るって「糸」の軌道を逸らしたが――追撃してきた四本の「糸」に胴を殴打されて瓦礫の山に墜落し、したたかに背中を打ち付けた。
「ぐっ!」
その瞬間――真里亞が展開した隔絶空間が揺らぎ、すぐさま元に戻る。
「……反射的に顔を庇ったか」
「!」
眼前の雑居ビルに亀裂が走り、崩壊する。電線を断ち切り、コンクリートの塀を薙ぎ倒して、異形の怪人――「ブラッドレス・ラヴェナス」が、現れた。
「人間として普通の反応だね。普通すぎて面白くない。最初は驚いたけど、いざ戦ってみるとこんなものか、トリガーって」
「好き勝手言って……!」
「それが“普通”だから顔を庇う。それが“普通”だから友達を見捨てない。君の行動原理は分かりやすいね。孤立してたから依存してきたエリカも分かりやすかったし、駿は何がそんなに分からなくて、人間の女を怖がってたんだろう」
杭のように太く、鋭利な八本の脚。その先端でアスファルトを割りながら、ラヴェナスの巨躯が近づいてくる。二階建ての屋根ほどの高さにあるその顔は、宿主だった人間を嘲り、せせら笑っているように見えた。
と、その背後に――「影」が躍り出る。
「影」は目にもとまらぬ速さで屋根から屋根を渡り継ぎ、大きく跳躍。ラヴェナスの直上に舞い上がると、彼の「仮面」目掛けて両手で握った短刀 の刃先を振り上げる。
「っ、プリンシパルか!」

蜂の一刺しのようなその斬撃は――しかし、ラヴェナスの「仮面」の直前で、バツの字に交差させた二本の脚に、阻まれた。
「……あら。完全に不意を突いたと思いましたのに」
短刀 がラヴェナスの脚を削り、激しい火花が舞う。鍔迫り合いの中でも余裕を崩さないプリンシパルと同様に、ラヴェナスもまた、満足そうに「惜しかったな」と言った。
「疾く、鋭い。ここまで俺に接近できたのは君が初めてだよ、プリンシパル」
「お褒めの言葉、光栄ですわ」
「どうだい。あんな人間さっさと乗っ取っちゃって、俺たちの側につかないか?」
まるで女を口説くように、ラヴェナスは甘い声で語り掛ける。その声色には、同類であるプリンシパルへの好意、偽りの世界 への諦念、そして、人類種である真里亞への侮蔑がないまぜになっていた。
「……」
このまま押し合っていても決めきれないと判断したのか、プリンシパルが短刀 を引く。蜘蛛の脚を踏み台にして後方に飛び退くと、軽やかに何度か回転し――彼女は、真里亞の前に降り立った。
「どうせ偽りの世界なんだ。さっさと世界中の人々をアナザーにしてあげるのが救済だと思うけどね。少なくとも、俺の宿主はそのつもりで体を譲ってくれたよ」
「……プリンシパル」
立ち上がっていた真里亞が、耳を貸すなと言いたげに呼びかける。プリンシパルは彼女を振り返り、ボロボロになったその戦闘装束を見て――くすり、と笑った。
「ラヴェナス、哀れなお方。人間の愛おしさを知らないなんて」
「……そうか」
“失恋”を悟ったラヴェナスの声色が、変わる。
「俺が女を口説くのは一回きりだ。残念だけど……死んでくれ」
ラヴェナスの人間の上半身が右腕を振り上げる。地面に垂れていた五本の「糸」が波打ち、鞭のごとく二人に襲いかかった。真里亞とプリンシパルが二手に分かれてビルの残骸に隠れると、今度は左腕の――真里亞側の「糸」を叩きつけるように振り下ろし、その残骸を粉々に破砕する。
「くっ、視界が…………っ!?」
巻き上がった土煙の奥に、ゆらりとラヴェナスの巨体の影が覗く。真里亞の頭上から蜘蛛の脚が振り下ろされ、刀で受けた彼女の小さな体を、軽々と吹き飛ばした。
「ぐうっ!?」
「君はどうでもいい」と、ラヴェナスが言う。「その辺で転がってろ」
「本当に、女性をモノか何かのように……!」
短刀 を構えて信号機に飛び乗りながら、プリンシパルはラヴェナスを睨む。と、四方、いや八方から「糸」が襲い来て、彼女はすぐさま飛び退いた。残された信号機がひしゃげ、叩き折られる。
「まずは君からだ。プリンシパル」
そう言って、ラヴェナスは再び右腕を振るった。
屋上に着地しようとしていたプリンシパルの背後から「糸」が迫る。と、プリンシパルは空中で姿勢を変え前方に回転、ハンドスプリングの要領で本来の着地予定地点より手前に手をついて「糸」に自分を追い越させると、今度は横方向に身を捻って上を向き、横薙ぎに「糸」を断ち切った。
「迎撃するだけなら容易い……ですが」
「そう。賢い君なら分かるだろう。君はもう、俺には近づけない」
右腕の「糸」を逃れたプリンシパルに、左腕の「糸」が迫り来る。その隙に右腕の「糸」が再生し――キリがないと判断したのか、彼女は回避優先に切り替える。
電柱を、信号機を、屋根を。飛び移るプリンシパルを追いかけるように、「糸」の爆撃が次々と降り注ぐ。時に角度を変え、時に高度を変えても一「糸」乱れることのないその攻撃に、プリンシパルとラヴェナスの距離が、少しずつ離れていく。
考える暇も、息つく暇も与えぬ飽和攻撃。自らは動かずに両手を振るい、自由自在に「糸」を操るその姿は、まるで異形の指揮者のようだった。
「……流石はブラッドレス。人を捨てた者ならではの力ですわね」
呟いて――プリンシパルは“ある場所”を見た。
そこには、“あるはずのもの”がない。
それだけを確認して、プリンシパルは目を細める。
「ならば、こちらは…………あら?」
古めかしい、街灯の上。
そこに着地したプリンシパルの周囲が――完全に、更地になっていた。
誘導されていたのだろう。彼女の進路にもはや飛び移る場所はなく、かなり離れた先に、半壊し、内部の鉄骨が剥き出しになった高層ビルを残すのみだった。
「……私としたことが。こんな単純な狙いに気付けないとは」
自嘲気味に笑って、プリンシパルはラヴェナスに向き直る。
「そんなこと言わないでくれ。君は……多分、いい女だったよ」
その街灯は、特等席に――「指揮」を続けていたラヴェナスの正面に、建っていた。
「でも、お別れだ」
まるで、恋人に別れを告げるかのように。
ラヴェナスが、右手から「糸」を放つ。
これまでのような鞭状の攻撃ではない。直線状に放たれた五本の「糸」は、音速を超えた矢となってプリンシパルの四肢を貫き、絶命させる。
――はず、だった。
「“何か”を、忘れているのではなくて?」
ちらり、と。一瞬、地上を見て。
プリンシパルは、ムーンサルトのごとく、跳んだ。

後方へと半月を描くそのおとがいの直上を、「糸」が通り抜けていく。この期に及んで抗おうとする彼女に興が削がれたのか、ラヴェナスは嘆息し、追撃を繰り出そうとして――彼女が「見た」場所に“誰もいない”ことに気が付いた。
「……! トリガーは!?」
「はあああああああああああっ!!」
上空。絶叫が耳を衝く。
鉄骨が剥き出しになった高層ビル。その上層階から――篝火真里亞が、降ってきた。
「チッ!」
右腕を振り上げ、プリンシパルに放った「糸」を真里亞に差し向ける。
「矢」から、再びの「鞭」へ。
唸りを上げてしなり、硬度と速度を兼ね備えたその一振りは、“普通”の人間であれば反射的に防御を優先する。そんな、致命的な一撃だった。
地上に舞い降りていくプリンシパルが、言う。
「……ラヴェナス。結局、貴方は人間 を分かっていない」
真里亞は――守らなかった。
刀の柄に手を添えたまま、僅かに体を回転させて致命傷だけを回避する。戦闘装束が吹き飛び、体中から鮮血が噴き出しても――彼女の目は、ラヴェナスのみを捉えていた。
「なっ……!?」
真里亞が、刀を抜く。
瞬間、片方だけ視力が悪い真里亞の右目――その瞳孔の中に、プリンシパルではない 、何か別の存在が揺らめき――宙に舞った鮮血が渦を巻いて収束し、刀に宿った。
「やああーーーーっ!!」
大上段からの、轟然たる斬撃。
その一太刀が、ラヴェナスの右肩を、切断した。
「が、あああああっ!?」
ラヴェナスの巨体が、初めてたたらを踏む。落ちていく右腕に苦悶の悲鳴をあげて大きく仰け反り、それでも体勢を立て直そうとした彼の耳に聞こえてきたのは――くすり、という上品な笑い声だった。
「――それでは、ハイライトと参りましょう」
プリンシパルが、短刀 を構える。
「ふ、ざ、けるなああっ!!」
蜘蛛の脚を振り上げて、ラヴェナスが激昂する。プリンシパルの体を貫き、踏み潰さんと振り下ろされたその脚は、しかし次の瞬間、短刀 によって体から斬り離されていた。
「一撃目――ゆるやかに ――」
「!?」
言葉とは裏腹に、アナザーですら知覚できない速度で跳び上がったプリンシパルが空中に現れる。まるで時間が止まったかのように滞空する彼女が次の足場にしたのは、今まさに斬り落とされ、落下していく脚の残骸だった。
「二撃目――柔らかく、優美に ――」
捻りを加えながら前方に宙返りし、破れかぶれに放たれた「糸」の上を行く。
すれ違いざま、弧を描くような斬撃がラヴェナスの左肩を破壊し、抵抗の術を奪い去る。そのまま軽やかに、そして優美に彼の眼前まで舞い上がったプリンシパルは、その「仮面」に短刀 を突きつけ、
「終撃――目を離さぬように ――」
袈裟懸けに、「仮面」を破壊した。
斬り下ろした勢いのまま、プリンシパルが滑るように着地する。何が起きたのか、それをラヴェナスが認識できたのは、それから数瞬後のことだった。

「バ、カな…………!?」
仮面を失ったラヴェナスの体が形を保てなくなり、亀裂が広がっていく。
プリンシパルはそんな彼を一顧だにすることなく、地面を血で濡らし、力なく横たわっている真里亞のもとに歩み寄った。
「……残念。あなたの≪グラン・パ・ド・ドゥ≫、ほとんど見えなかったわ……」
プリンシパルの三連撃を指して、真里亞が言う。その確信めいた言い方は、自分の相棒が決着をつけたことを微塵も疑っていない口ぶりだった。
「また無茶をして……。あんな戦い方をしていたら、命がいくつあっても足りませんわ」
「同級生を捨て駒にされたのよ……? 普通の女の子なら、どうする……?」
「……一発、ぶん殴って差し上げます」
「でしょ? ふふっ……」
返事代わりに微笑んで、真里亞は気を失う。と、主を失った隔絶空間が維持力を失って、少しずつ解除され始めた。
「……分から……ない……」
かすれた声が聞こえて、プリンシパルはラヴェナスを見上げる。
「プリンシ、パル……。お前の言う、人間、とは……なん、だ…………?」
「……揺れ動くもの」
彼を弔うように、プリンシパルは答える。
「例えば、しょせん自分は普通の人間にすぎないと自虐 しながら、心のどこかで、いつかは主人公になれると自愛 する。そのように相矛盾する心の間で揺れ動くからこそ人間は愛おしく……それゆえに、トリガーには二つの力 が宿るのです」
「理解、でき……ない……。お前が……何を、言ってるのか…………」
ラヴェナスの仮面の下に覗く口元に、皮肉めいた笑みが浮かぶ。
同時に、その巨体が崩壊を始めた。
まるで乾いた粘土のように、白化した体が破片となってずり落ちていく。人を捨て、体を変質させたがために、その傷口から血は流れない。
昇藤駿、あるいは、ブラッドレス・ラヴェナス。
その終幕を最後まで見届けて、プリンシパルは音もなく夜の帳の中に消えた。
■
「エーリカーっ! お見舞いに来たよー!」
「お、お邪魔します……」
「えっ? 根本さん、垂木さん……篝火さんも? どうして……」
翌日の放課後。ランとスミレの提案で、真里亞はエリカが入院している病室を訪れた。
寝耳に水といったエリカの反応もむべなるかな、彼女はここ数日の記憶が欠落しているらしい。その間まともな食事を摂っていなかったため重度の栄養失調に陥っていたとのことで、彼女の腕には見たことがない量の点滴が繋がれている。
「そうだったんだ。篝火さんが私を……」
「でね、エリカを安全な場所に運んでホッとしちゃったらしくて、真里亞ってば階段でずっこけて転がり落ちたんだって! ウケるよねー!」
「いや、笑い事じゃないのだけど……」
片や、ラヴェナスの「糸」に切り裂かれた真里亞の体も全身包帯だらけであった。彼女の体に宿るもう一人のアナザー――「血」を操る彼女 が体内で手を貸してくれたのかどうかは分からないが、意識を取り戻した時点で傷は比較的浅くなっており、幸い、傷痕も残らずに済むらしい。
昨晩、ラヴェナスが消滅してから一時間と経たないうちに、“Spider”は「サービス終了のお知らせ」を発表した。想定していなかった不具合によって未成年者が利用できてしまっていたため、というのが終了の建付けである。
時系列を考えれば、“Spider”にラヴェナス以外の者が関わっていたのは間違いない。それが何者なのか、また別の形で怪人化を推し進めようとしているのかどうかは気がかりだが――少なくとも“Spider”による被害の拡大はなくなったことに、真里亞は安堵していた。
「あの」
と、エリカが真里亞を見る。
「私を見つけてくれた時、他に誰かいなかった?」
「えっ? あ、いいえ。一人だったわ」
真里亞は咄嗟に嘘をついた。お縄になった男のことなど敢えて伝える必要はない。
しかし、エリカが探している「誰か」とは、別の男のことのようだった。
「……彼氏と、連絡が取れなくなっちゃって」
「か、彼氏さんって……噂の、大学生の?」と、スミレが食いつく。
「彼氏だと思ってたのは私だけかもしれないけど……。たくさんお金渡して、たくさん……やりたくないことさせられて。あんな関係、どうして変だと思わなかったんだろう……」
「エリカ……」
「自分は他の子とは違うんだって、こんなハイスペックな彼氏がいるんだって……。バカだったわ、私……」
誰にともなく言葉を続けるエリカの横顔は、深く自分を恥じているように見えた。
確かに、始まりこそ彼女の虚栄心がきっかけだったのかもしれない。だが、ブラッドレスの干渉を受けた人間は――真里亞は未だその詳しい原理を理解しきれていないが――自分の中に潜んでいた負の感情を増幅され、正常な判断力を失い、何かに病的に依存するように仕向けられていく。真里亞からすれば、エリカは純然たる被害者であった。
「ええと、時園さん」
とはいえ、そのままそれを伝えるわけにもいかない。こういう時に気が利いた一言が出てこない自分を恨みながら、真里亞はとりあえず何か言わなければと口を開いた。
「――私、勝負下着を持ってないの」
「「「……は?」」」
ラン、スミレ、そしてエリカまでもが、呆気に取られたように真里亞を見た。
「あ、違う! ええと……」と、真里亞は慌てて取り繕う。「私たちくらいの歳なら、そういう下着の一つや二つ持ってるのが普通なんでしょう? 持ってないって言ったらそこの二人に弄り倒されたし、私は他の子と違うんだって焦ったけど……、心のどこかでは、普通じゃないことが嬉しかったりもして。あ、つまりね、自分が“特別”だと思いたい気持ちは誰でも持ってる“普通”のことだから、気に病まないでと伝えたいのだけど……」
「勝負下着の前フリいらねえ~~!」
「ま、真里亞ちゃん……! そんなに心残りなら、この後買いに行っちゃおうか……?」
ランが頭を抱え、スミレが目を輝かせる。そして肝心のエリカには全く意図が伝わっておらず、彼女は病床で目をぱちくりさせていた。
「ええと……篝火さん。きっと励まそうとしてくれたんだよね、うん」
「うわ、エリカの目が生暖かい」
「だ、大丈夫……! わたしは真里亞ちゃんの味方だよ……!」
「雑なフォローはやめて! 滑ったのは分かってるから!」
いたたまれなくなった真里亞は身を翻し、「お茶でも買ってくる」と言って病室の出口に向かった。「あ。わ、わたしも一緒に」「スミレ。一人にさせてあげなよ」という友人二人のやり取りに心をグサグサと刺されながら、逃げるように扉に手をかける。
「篝火さん」
そんな真里亞の背中を、エリカが呼び止めた。
「まだ、言ってなかった。……ありがとう。」
ぎこちないながらも、その口元には笑顔が浮かんでいる。同級生を遠ざけていたかつての彼女とは違う、どこか幼さを感じるその笑い方に――いつか満面の笑顔が見たいなと思いながら、真里亞は穏やかに微笑み返した。
「気にしないで。普通のことをしただけだから」
Episode: principal 完