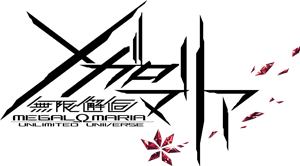どうしてこんなことになったんだろう、と
「……たった二万円か。もう少し稼いできてくれると助かるんだけどなあ」
学年で一番の美人。高校三年生でありながら医大生の彼氏を持ち、同級生の男子にとっては話しかけるだけでも勇気のいる高嶺の花。自分はそんな存在だったはずだ。同級生の女子からは子どもっぽい嫌がらせをされることも少なくなかったが、それは一足先にオトナの世界へ足を踏み入れた自分に対する妬み嫉みによるものだと思えば気にもならなかった。
何かがおかしくなり始めたのは、目の前の男――エリカ自慢の彼氏が、「学費が足りない」などと言って、彼女に金をせびるようになったのがきっかけだった。
「ご、ごめん……。明日も別の男の人とごはん行ってくるから」
「ごはんだけ?」
「えっ?」
男の手がぬっと伸びてきて、エリカの頬を撫で、首筋へと下りていく。
「お前かわいいんだからさ。もっと稼げる方法があるんじゃないかなーって」
「そ、れは……」
不穏なのに心地よく感じてしまうその手から一歩引いて、距離を取る。エリカは箱入り娘で世間知らずだが、今の言葉の意味が分からないほどには
「嫌?」
「嫌、というか……。私はあなたの、
「……そっか」
そう言うと、男は特徴的な青い目でまっすぐエリカを見て、微笑む。
「嬉しいな。ありがとう」
エリカが好きになったのは、彼のその青い目と、笑顔だった。
学校では――高嶺の花といえば聞こえはいいが、つまるところ彼女は「異物」として、距離を置かれていた。事業に夢中になっている両親には初めから期待していない。こうやって目を見て微笑みかけてくれる存在は、彼が初めてだった。
こんな笑い方をできる人が、悪い人なわけがない。
――と、思う。
医大に通うにはお金がかかると言うし、彼なりに自分を頼ってくれている。
――の、だろう。
「おっ、通知来てら」
エリカが自分に言い聞かせていると、スマートフォンを取り出した彼が見慣れたアプリを立ち上げるのが目に入った。彼と出会えたきっかけであり――今も「“お食事相手”を探すため」と説かれて使い続けている、“Spider”というマッチングアプリである。
「あ、あはは……。駿くん、まだやってたんだ」
――嫌な予感に、胸がざわめく。
不安を抑え、エリカはおずおずと問いかけた。
直接「他の女の人と会っているのか」と問い質すことはできなかった。そんなことをして怒らせたら捨てられるのは自分の方だという恐怖が、彼女の言葉を縛り付けていた。
「……お前さあ」
そんなエリカの態度を見て、男は、少し意外そうに目を瞬かせた。
「最近、幻聴が聞こえたりしない? 寝る前とかに」
「えっ? なんでそれを……」
「あ、やっぱり……! すげぇ、思ったより早かったな!」
――胸のざわめきが、大きくなっていく。
男は、心から嬉しそうに笑っていた。
エリカが恋したはずの、その笑顔。しかし、それは彼女ではなく、
「そうか……! お前みたいに学校で孤立してる奴の方が依存しやすいし、
「な、何言ってるの……?」
エリカは男に縋りついた。そうしなければ、昏く深い穴の底に落ちてしまいそうだった。
「おい、離せよ」
――胸の奥底で、蛆虫のような何かが蠢き、のたうち、せり出してくる。
「
「えっ――」
何か、壊れてはいけないモノにヒビが入るような音が、胸元から聞こえた。
呼吸もままならないまま、恐る恐る視線を下げていく。そんなはずはない、そんなことは起こりえないと必死に否定しながら見た、自分の胸元。そこには――
「いっ……!」
目。
何者かの“目”が、ぱっくりと胸に開いた裂け目から、エリカを見つめていた。
「嫌ああああああああああああああっ!!」
■
それは、勝負下着であった。
「……あの、二人とも。私が選んでほしかったのは服なんだけど……」
百貨店の一角にある、レディース向けの衣料品店。
その試着室の前で――ハンガーにかかった上下セットの下着を片手に――篝火真里亞は、人選を間違えた、と後悔していた。
「いやいやいや。男の気を引くために着てく服なんでしょ? 『いざ!!』という時のために内側からオシャレしてった方がいいって。あたしもそれで彼氏オトしたし」
片や、根本ランは、色仕掛けを万能の駆け引きツールだと信じていて。
「ひ、必要なのは、オトナっぽさかと……。真里亞ちゃんが好きになった子だもん、きっと可愛い男の子、こほん、オトナっぽさに弱い子のはずだし、その下着でガツンと……!」
片や、垂木スミレは、
「あなたたちは何を言ってるの……?」
どこから訂正すればいいのか分からず、真里亞は目頭を押さえる。
確かに、「男の気を引く服を選んでほしい」とオーダーしたのは彼女の方である。慢性的な金欠のせいで一山いくらの衣類ばかり買っていて流行や相場にも疎いため、友人のアドバイスを必要としていたのも事実だ。だが、それ以外が全部間違っている。
「あのね、ラン。何か誤解してるみたいだけど、いざという時なんて来ないわ」
「いーや、最初はみんなそう言うんだよ。でも、予想外にやってくるから『いざという時』なんじゃん? 来てから後悔しても遅いじゃん?」
「無駄に理屈をこねてくるわね……。脳内ピンクのくせに」
「い、淫行条例で捕まらないように気を付けて……。あっ、あとで感想教えて、ね」
「だから年下じゃない!」
色恋の話に興味津々なのか、友人二人は目を輝かせて迫ってくる。何を言っても無駄だと判断した真里亞は、強引に話を切り上げるべくハンガーを突き返そうとして、
「とにかく! こんなのはいらないから、服を――」
「それに、
「――えっ?」
ランが言った一言に、腕を止めた。
「そ、そうなの?」
毅然としていた真里亞の声に戸惑いの色がにじむ。スミレに視線を向けて確認を求めると、彼女は申し訳なさそうに苦笑していた。
「え、えっと。真里亞ちゃんみたいに……全部が綿100%ってことは、ないかな……」
「うっ……!?」
友人たちの言葉に、真里亞のアイデンティティが揺らぐ音がした。
――「普通の人間」でありなさい。
彼女が10歳の時、両親と共に事故で命を落とした祖母との約束を、真里亞は不器用なりに守ろうと努力してきた。天涯孤独の身でありながら特別扱いを受けることを嫌い、学校の成績も、普段の言動も、完璧なまでに「普通」にこなしてきたつもりだった。
それが、こんなことで普通ではなくなっていたとは。
改めて手元のハンガーを見る。繊細なレースが華やかな黒の上下セット。しかも、レース部分が妙に広くて肝心の布地が少なく、必要な部分を最低限にしか隠さない、いかがわしい構造になっている。
「こんなものを、みんな普通に持ってるのね……」
真里亞は感心した。
「えっ?」
思わずといった様子で、スミレが目を丸くした。
「え、えっと、さすがにそんな大胆なやつはあんまり……むぐっ」
「いいからさ。試着してみなよ、真里亞」
おずおずと話し出したスミレの口を、ランが塞いだ。
「ほら、真里亞って新体操部じゃん? レオタードみたいなもんだと思ってさ、ね?」
悪戯っ子のようなその笑顔には「こんなおいしいシチュエーションを逃してたまるか」という文字が浮かんで見える。真里亞は嫌な予感がして、改めて問い直した。
「……今、スミレが聞き捨てならないことを言いかけた気がするんだけど。本当に、みんな持ってるのよね?」
「はーい。試着室のドア閉めまーす」
「ちょっ、質問に答えなさい! 本当なのよね!? ラン、スミレ――!!」
――個室タイプの試着室の扉が、無情にも閉められた。
もちろん内鍵で、閉じ込められたわけではない。しかしこうなった以上、彼女たちを満足させなければ「服のアドバイスをもらう」という目的を達成できないことは明らかだった。
「し、試着するの? これを?」
絶対に嫌だ、と真里亞は思った。
鏡に正対し、ハンガーにかかったままの下着を体の前面に当ててみる。漆黒の学生服に黒の下着が溶け込んで分かりにくいが、自分に似合っていないのは明らかだった。
こういうのは、もっと成熟した、オトナの女性のための一品。
真里亞がそう判断し、直ちに試着室の外に出るべくドアノブに手をかけた時だった。
『――本当は、一着くらい欲しいんでしょう?』
頭の中に、からかうような声が響き渡った。
「…………」
ドアノブから手を離し、鏡に向き直る。
家族を喪った事故のせいで、片方だけ視力が悪い真里亞の右目――その瞳孔の中に、
『似合わないって言い聞かせているけれど、心のどこかで素敵だとも思っている……。分かるわよ、私は貴方だもの』
「……」
『試着する勇気が出ないなら、お姉さんが体を借りて、代わりに着てあげましょうか?』
「……はいはい。余計なお世話よ」
明確な拒絶を含みつつ、しかし慣れ親しんだ様子で、真里亞は
確かに、
「あなたは私かもしれないけど、あなたは私の全てじゃない。体は渡さないわ」
『あら、つれない子ね』
「でも、ありがとう。おかげで本来の目的を思い出した」
そう言って通学鞄からスマートフォンを取り出し、ロックを解除する。既に起動していたアプリが立ち上がり、自分のプロフィール――趣味や好きな男のタイプ、恋愛観など――が記された画面が表示された。上部のバナーには、「誰それから『いいね!』が届きました!」「新しいメッセージが届いています!」といった、賑やかな通知が並んでいる。
男女が出会うための定番ツール、マッチングアプリ。
その中でも、つい最近β版のサービスを開始した“Spider”というアプリである。
本来、マッチングアプリは法的にもアプリストアでも規制されていて、18歳以上であることを証明しないと登録することができない。だが――この“Spider”に限っては、ある方法で年齢を偽装すれば、その規制を回避して登録できるという情報が出回っていた。
事実、真里亞もその方法で年齢審査をくぐり抜け、こうしてアプリを利用している。念のため調査用に新規契約した二台目のスマホを使っているが、スパイウェアの類が紛れ込んだ形跡もない。恋に夢見る高校生たちがこんな機会を逃すはずもなく、違法にアプリを利用する会員の数はうなぎのぼり、らしい。
――“Spider”を利用していた女子高生が、「怪人」に姿を変えた。
そんな噂が囁かれ始めたのも、それと同じ時期のことだった。
もちろん都市伝説に近い噂である。「目撃談」とされるものに確たる証拠が添えられていたことはなかったし、ましてや “怪人化”と“Spider”との因果関係など証明しようもない。
「……女の子をたぶらかして、“
だが、真里亞は確信していた。
「でも、一人なのか組織なのか、同じアカウントを使い続けているのか、アカウントの転生を繰り返しているのか……これ以上は、
男たちのプロフィールを眺めながら、真里亞は
『登録者は無数にいるのよ。真里亞ちゃん一人で見つけ出せるとは思えないけれど』
「何もしないよりはマシでしょ」
『それに、せっかく会えても初回のデートでお断りされてばかりだし……』
「う、うるさいわね! だから服を買いにきたんじゃない!」
呆れたような
『まあ、試行錯誤する真里亞ちゃんも可愛いけれど……あら?』
なぜか保護者目線の
「いけない。待たせすぎちゃったかしら」
『ああ、それはごめんなさい♪ お買い物、楽しんでね』
右目の揺らめきが瞳の奥に消えていくのと同時に、
結局、下着の試着はしていない。ランとスミレに申し訳ないことをしたな、と考えつつ、真里亞は謝罪の言葉を準備しながら鍵を開ける。
「二人とも、ごめんなさい。実はまだ――」
だが、その心配は杞憂に終わった。
「ヤバいヤバい! ヤバいもの見ちゃった!」
息せき切って、ランが試着室に雪崩れ込んでくる。彼女の頭からは、下着のことなど吹き飛んでいるようだった。
■
「ほら……! あれ、エリカじゃない!?」
百貨店を飛び出して、夜の帳が近づきつつある繁華街を歩く。見失わないよう尾行を担当していたスミレと合流するや否や、ランが通りの前方を指差した。
「エリカ……って、時園さん?」
「そう! 一年で同じクラスだった時園エリカ!」
正直、真里亞としてはさほど親しくもなかった同級生である。何をそんなに動揺しているんだろう、と思いながらランが指差した先を目で追う。
繁華街から抜け出して、人通りの少ないホテル街へと続く、その道の途中。
そこに、彼女はいた。
「ああ、見つけた。確かに時園さ……えっ?」
スーツ姿の、小太りの男。彼女はその男に寄り添って、歩いていた。
腕を組んだり、手を繋いだりして歩いているわけではない。しかし、男がエリカに向ける粘ついた眼差しや下卑た笑顔が、父娘のような関係ではないことを示していた。
「な、何あれ。どういうこと……!?」
「何って、見りゃ分かるでしょ!
予想だにしなかった光景を前に、真里亞の頭が真っ白になる。そんな彼女に現実を突きつけるように、ランが鋭い口調で言った。
「あんたたちは知らないかもしれないけどさ、『エリカが売りやってる』って、前から噂になってたんだよ。あたしも信じられなかったけど……あれ、まさにじゃん」
「あ、あの二人……。さっきのデパートで、真里亞ちゃんに渡したのと同じような下着を、い、いっぱい、いっぱい買ってたの……!」
「そんな……」
学校での時園エリカは――気高い人の、ように見えた。
そのイメージとのあまりの落差に、真里亞は言葉を失う。同じく動揺を隠せないスミレが「で、でも、エリカちゃんって……最近彼氏できたんじゃ……?」ともごもご呟いたが――その問いかけに答える者はいなかった。
男の話に応答するエリカの横顔からは、何の感情も読み取れない。少なくとも男に対して好意的でないのは明らかだが、かといって嫌悪感を滲ませることもなく、機械的に対応しているように見える。
「ねえ。なんか様子がおかしくない……?」
より正確に言えば――生気がないのだ。
まるで、何者かの言いなりになっているかのように。
「確かに」と、ランが眉根を寄せた。「デパートで見かけた時からあんな感じだわ。あんまりにも雰囲気違いすぎて、あたし最初エリカだって気付かなかったもん」
「…………」
最悪の予感が、脳裏をよぎる。
あのような顔をした
「……ねえ、スミレ。時園さんって、彼氏とどこで出会ったの?」
「えっ? えっと、なんだっけ、ランちゃん……。さ、最近話題の……」
「あーそうそう、言ってたわ。マッチングアプリだよ」
――“Spider”。
スミレとランが顔を合わせて口にした名に――最悪の予感は、確信に変わった。
「……二人とも。警察呼んできて」
「えっ……?」
「私が見張ってるから! お願い!」
返事を待たずに、真里亞は駆け出した。
どこかで角を曲がったのか、エリカと男の姿は見えなくなっている。真里亞も、友人たちが戸惑っている間に適当な路地へと折れ、二人の視界から姿を隠した。
おおよその当たりをつけ、まだ人の少ないホテル街を駆ける。不本意にも蓄積されたこれまでの経験から、エリカたちが向かうであろう場所は何となく分かっていた。
ホテルには入らない。人の目の匂いがするから。
幅の広い道ではない。標的に逃げ回られるから。
向かうのは、エアコンの室外機や廃棄品の段ボールなどが積まれた、暗がりの路地。
「――おごぉっ!!」
その一角から――悲鳴が、聞こえた。
「が、はっ……!! う、ううっ……!!」
凄まじい膂力で吹き飛ばされたのか、エリカと共にいた男が、値札がついたままの下着をまき散らし、呻き声をあげて地面をのたうち回っていた。
「っ! あの人……!」
『――待って、真里亞ちゃん』
男に駆け寄ろうとした真里亞を、
ふと足を止めると、街灯の光が届かない路地の奥から、呪詛のような言葉が聞こえてきた。
「コノ……偽リノ世界ニ、黄昏ヲ……」
「……時園、さん」
「コノ……偽リノ世界ニ、黄昏ヲ……コノ……偽リノ世界ニ……」
焦点の合わない目で立ち尽くし、壊れたラジオのように同じ言葉を繰り返し――そして、片手の掌に“仮面”を持った時園エリカを見て、真里亞の顔が悲痛に歪む。
「ア、ア……! アアアアアアアアアッ!!!!」
時園エリカが、“仮面”を身につける。
同時に、禍々しい瘴気が吹き上がり――彼女の体が変質した。
仮面と共に素顔を覆う、髑髏のような頭部。吊るし糸の切れた骸骨のように猫背で立つ、細身の体。左手に携えた鎌と、右の手首から伸びる逆刃が鈍く輝く、死神の尖兵。
人の絶望を餌に育ち、内側から宿主を食い破る、異形の怪人。
「アナザー……」
エリカを弔うような真里亞の呟きが、宵闇に溶けて消えていった。
――アナザー。
それが巷で騒がれている「怪人たち」の正式な呼称であることを、真里亞は最近知った。
人は誰しも、心の奥底に秘めた“本性”がある。
アナザーは、その“本性”が物理的な実体を持った存在である、とされている。意思疎通ができるほどに「開花する」ケースはほとんどないが、アナザーは世界中のあらゆる人の内側に存在し、個々人の“本性”=個性を反映して、姿形も異なるという。
『でも、目の前にいるあの子――シーカー・タイプは違う』
臍を噛むような声色で、真里亞の頭の中の
『あれは、他人の悪意によって強制的に「開花させられた」アナザーよ。外見に個性がない量産型だし――自我も壊れてるから、より上位の怪人の命令に従って動いている』
「……もう、手遅れだったってことね」
恐らく、真里亞が追い付いた時点で、あるいはランとスミレがデパートで見つけた時点で、時園エリカは時園エリカではなく――怪人が、彼女に化けていたのだろう。何者かの命令を受けて、目の前の男を誘い出すために。
「だ、誰かっ!! 助けてくれぇっ!!」
「!」
男の叫びが、真里亞の意識を現実に引き戻した。
まだ痛みが残っているのか、それをも腰を抜かしたのか、男は立ち上がれずにずるずると地面を這って逃げている。その奥から、エリカ・アナザーが一歩ずつ迫っていた。
左手の鎌が男に向けられている。仮面の下で冷たく光る瞳が、エリカ・アナザーの意図をはっきりと表していた。
男を、仕留めようとしている。
「っ……!」
『……真里亞ちゃん、分かってるわね』
真里亞の焦燥を見透かしたように、
『私たちの目的は、あの子をあんなにした犯人を見つけ出すこと……。今も、そいつは近くにいるかもしれないわ。ここで手を出して、顔を覚えられたら――どうすることもできなくなる』
「分かってる! 分かってるわよ……」
真里亞は吐き捨てるように答える。理屈の上では、彼女の方が正しいことは分かっていた。
それでも。
『あの子はもう、生きているか死んでいるか分からないし……真里亞ちゃん?』
それでも――
「っ、ええいっ!!」
手近に落ちていた廃材の木片を掴み、投げつける。新体操のバトン投げの要領で投擲された木片は風を切って飛び、エリカ・アナザーの右肩に直撃した。
「…………?」
金属が軋むような鳴き声を上げて、エリカ・アナザーが真里亞を見る。真里亞はその隙に男とエリカ・アナザーの間に割って入り、両腕を広げて仁王立ちした。
「逃げてください! 早く!」
「あ、ああ……! ああ……!」
地面に伏していた男は今度こそ身を起こし、這うように逃げていく。ぎこちない動きで彼を追いかけようとしたエリカ・アナザーの横顔に、真里亞は再び木片を投げつけた。
「ダメよ、時園さん……! 行かせないわ」
『真里亞ちゃん……!』
「分かってる。まだ、あなたの力を借りる時じゃない……。でも、時園さんが人殺しになるのを黙って見てるわけにもいかない!」
『生身でアナザーと戦うつもり!?』
「ギ、ギ……!! ガアアアアアッ!!」
再び邪魔をした真里亞を「敵」と認識したのか、エリカ・アナザーが吼える。
「っ……!」
見え見えの斬撃ではあるが、振り下ろす速度が人間のそれではない。予測して回避行動を取ったにもかかわらず、真里亞の制服のリボンが結び目から真っ二つになった。
『まだよ!』
続いて、左手の鎌が横薙ぎに迫る。人間の反応速度を超えた一撃だったが、真里亞は
避けきれずに断ち切られた長髪の一部がパラパラと落ちていく。あと一瞬でも動くのが遅れたら地に転がっていたのは自分の首だったと想像して、真里亞はぞっと身震いした。
「ア……ア、ア……」
まるで壊れた時計の秒針のように、エリカ・アナザーはカク、カク、と首を一定の角度で傾けては戻し、傾けては戻して真里亞を見ている。関節ごとに順序良く手足を動かすさまといい、その動きは昆虫のそれに近い。
「まさに“怪人”ね……」
元より正面から戦うつもりはなく、男を逃がしたら自分も逃げ出すつもりだった。だが、その方法が見つからない。一瞬でも背中を見せようものなら、彼女は怪人の膂力に組み伏せられ、体をバラバラに切り刻まれてしまうだろう。
じりじりと後ずさりながら真里亞が絶望的な状況に顔をしかめた、その時だった。
――ばさり、と。
背後から巻き付けられたゴミ袋が、エリカ・アナザーの視界を奪った。
「おーい、こっちこっち!」
驚き見ると、右前方の塀の陰に隠れて、見知らぬ男が手招きしていた。
「一般人!? こんなところに、誰……!?」
エリカ・アナザーに襲われていたのとは違う、若い男だった。年の頃は20代前半だろうか、ツーブロックに切りそろえられた短髪が爽やかな印象を与えている。
こんなところで何をしているのか分からないが、考えている暇はない。真里亞は急ぎ走り出すと、できるだけ物音を立てないよう、同じ物陰に滑り込んだ。
「あ、ありがとうございます……」
「いやあ、かっこよかったよ! 君、『マリア』ちゃんでしょ?」
「えっ……!?」
どうして名前を、と尋ねる前に、男は「これ」と自らのスマホを見せてきた。
そこには、真里亞のプロフィール――趣味や好きな男のタイプ、恋愛観など――が記された画面が表示されていた。それも、彼と「マッチング」した状態で、である。
「“Spider”……!」
「なんか騒がしいなって思って覗いてみたら、プロフで見た子がヤバいやつに襲われてるんだもん。つい体が動いちゃった」
エリカ・アナザーの様子を窺いながら、男は小声で囁きかける。
その青い目を見て、自分のことをハーフだと言っているアカウントがあったのを真里亞は思い出した。確か、「シュン」とかいう名前だったはずである。
「思い出してくれたみたいだね」
「は、はい……」
「じゃあ、逃げよっか。友達思いなのはいいけど、無茶はダメだよ」
そう言って笑うと、男は真里亞の手を取って歩き出した。この非常事態でも動じていないのか、あるいは動じていないフリを装っているのか、その足取りは頼もしい。
絶体絶命の危機に、助けてくれた男。
「……『シュン』さん。あなた、私が襲われてるタイミングで来てくれたんですよね?」
だが、真里亞は知っていた。知ってしまっていた。
人々の内に潜む、
そして、その
「どうしてあの子が――私の友達だって分かったんですか?」
繋がれた手を振り払い、真里亞は男を睨む。
男はしばし言葉を失っていたが――突如、その青い目をギョロリと見開くと、「鋭いね」と可笑しそうに笑った。
「賢い子は好みだな。好みだけど……もう、俺の女にはなってくれそうにないね」
「……時園さんも、同じ手口でたぶらかしたんですか」
「どうだろう。本人に聞いてみれば?」
『――真里亞ちゃん!』
一条の金属音が、背後を通り過ぎた。
「えっ?」
振り向くと、真里亞が背にしていた背の高いブロック塀が、その中ほどで横一文字に切断されていた。断面の向こうに、エリカ・アナザーの無感情な仮面と鈍く輝く鎌が見える。
ぐらり、と――古びた塀が真里亞の側に傾き、崩れ落ちてくる。
「……っ!」
悲鳴をあげる暇すらなかった。蓄積していた土砂が真里亞の頭上に降り注ぎ、次いで、崩壊したブロックの数々が彼女を圧し潰す。
路地裏に響き渡った轟音が収まる頃には――その場所に、
「……メッセージの感じでは、男に免疫がなくて騙しやすそうだと思ったんだけど。人間は難しいな」
心から不思議そうに首を傾げ、男は瓦礫の山を眺める。そして、切断された棚の向こうで糸の切れた人形のように立ち尽くしているエリカ・アナザーに労いの言葉をかけた。
「エリカ、ご苦労様。相手は変わっちゃったけど、どう? 初めて人を殺した気分は」
「……ア、ウ……!」
「苦しい? そうだろうね。君の中にはまだ、
男は手を伸ばし、エリカ・アナザーの頬を撫でる。愛おしげなその手つきは、時園エリカに向けたものとは違う――生まれたばかりの我が子を慈しむような手つきだった。
どこか遠くから、「真里亞!」と呼ぶ声が近づいてくる。
彼女の友人たちだろうか。派手にやりすぎたかな、と苦笑し、男が踵を返した――その時だった。
「……まだ、間に合うのね」
少女の命を呑み込んだはずの瓦礫が、動いた。
「まだ――時園さんは
「おいおい、ウソだろ……?」
瓦解したブロックの、その最も大きな破片を背中で持ち上げながら、少女が立ち上がる。頭部からは流血し、制服の所々が千切れているが、その眼差しは力強く――家族を喪った事故のせいで、片方だけ視力が悪い少女の右目――その瞳孔から、血潮の如き濃紅の炎が燃え上がっていた。
「まさか、お前も人間じゃないのか……!?」
男が――生身で
もはや、
刻限を告げるブザーは既に鳴り、状況という観衆は、“主演”の登場を待ちわびている。後は――舞台の幕を開けるだけだ。
「開演――」
右目の炎が収束し、紅きクリスタルの花が咲く。
「――プリンシパル!」

篝火真里亞が、“主演”の名を呼んだ。
彼女を中心に赤黒い血の色をした
「くっ……! トリガーだと!? こんな小娘が……!」
狼狽する男の声を切り裂いて――真里亞の中の

煌々と輝く橙色の瞳が、微笑むように揺らめく。武装的でありながら女性的でもある艶やかな体を行儀よく折り畳んで、
「お見それしたわ、真里亞ちゃん」
真里亞の格好もまた、戦闘装束に変化している。黒き長髪はそのままに、素肌を覆う薄手の装甲が、戦いへの覚悟を体現していた。
「友達を見捨てなかった貴女の選択が、犯人を釣り出した――本当の主演は、貴女なのかもしれないわね」
「……褒め言葉なら、あいつを倒した後に聞くわ」
血の色をした刀の柄を握り直し、真里亞は鋭い視線を男に向ける。プリンシパルは同じように男に向き直ると、くすり、と上品に目を細めた。
「大変お待たせいたしました。では――始めましょうか」
プリンシパルと真里亞がそれぞれの得物を構え、並び立つ。
「客席には興奮と感動を――」
「――貴方には、死を届けましょう」
芝居がかったその言葉は、しかし、おぞましいほどの殺意に満ちていた。
(つづく)