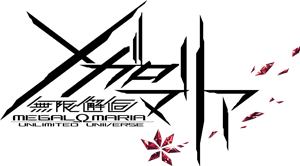アスファルトに散った桜の花弁を舞い上げながら、異形のモノたちが戦っていた。
「ギギギィッ!」
人語を解さぬ
「……学ばぬ奴よ。威力の問題ではないと解らぬか」
ぐにゃり、と。その刃の軌道が逸らされ、空しく街路を叩き割る。
原理不明の空間湾曲能力。渾身の一撃を軽くあしらった小柄な
緋袴の如き、紅の肢体。それは燃える炎の赤ではなく、「
「己が意思も持たぬ虫けらごときが――わらわに触れるな」
その言葉と同時に、パァン、とシーカーの首があらぬ方向に曲がった。
異形を異形たらしめていた仮面が破砕し、その下にあった少女の顔が露わになる。
その拍子に、砕け散った仮面の破片から――大粒の弾丸がひとつ、零れ落ちた。
「状況終了。ご苦労様です、アイスアイゼン」
敵に勝利した感慨を一切感じさせない声が、「アイスアイゼン」と呼ばれた
通信機器のようなものはない。アイスアイゼンの能力か、あるいはその宿主――トリガーが持つ能力なのかは定かではないが、
「フッ……。相も変わらずよき頃合いを見計らうものじゃ。今の狙撃など、わらわの言霊がこやつを滅したかのようであったぞ」
「そうですか」
「……少しは嬉しそうにせよ。わらわが称賛しておるのだ」
「早く帰宅して、睡眠をとらねばなりませんから」
つれない言葉が不満だったのか、アイスアイゼンが抗議の目で声の主を見る。
その視線の先――直線距離にして1キロメートルは離れた雑居ビルの屋上に、女性の人影があった。その手には、今しがた役目を終えた狙撃銃が鈍く輝いている。

「――人間の体というものは、不便ですね」
赤い菱形の髪飾りをつけた少女はそう呟くと、宵闇の中に姿を消した。
■
その日は、篝火真里亞が「まだ何も知らずにいられた」最後の一日であった。
都心から少し離れた郊外にある学生寮で、いつも通りに通学の準備をする。といっても、鞄の中身は前夜のうちに揃えてあるから、朝は身だしなみを整えるだけだ。
地域の人が見れば一目でどこの高校か判る漆黒のセーラー服の袖に腕を通し、友人から教わったやり方で軽く髪を整えたら、胸元にスカーフを結ぶ。まだひと月と使っていない新品のスカーフの鮮やかな赤は、彼女が高校3年生に進学した証であった。
「……さて、と」
登校時間を迎え、寮の廊下もにわかに騒がしくなり始めている。最後に鏡で服装に乱れがないかを確かめると――彼女は部屋の一角に設えてある小さな棚の前に正座で腰を下ろし、両手を合わせた。
その棚には、一葉の写真が飾られている。
7年前、かけがえのない人たちと全員で撮った、最後の写真。
「お父さん、お母さん……おばあちゃん。行ってきます」
数秒、静かに思いを捧げた真里亞は軽やかに立ち上がり、部屋の出口へ向かった。
屋外に出ると、
巨大剣――と、呼べばいいのだろうか。
まるで地球そのものに突き立てられているような、超・超巨大な西洋剣が、遠く西の空にそびえている。その刃先は地中深くに隠れ、その剣把は雲を貫いて遥か上空にある。あまりに非現実的なその光景は、しかし、今や人々の日常の一部となっていた。
――『神の剣・トワイライト』。
世界のどこにいても黄昏の方角に見えるその幻影の大剣を、人々はそう呼んでいる。例えるなら陽炎や虹のような光の現象に近く、こちらから近づこうとしても絶対に麓には辿り着けない。一見すると大地を貫いているその刃は、七年前に出現して以来、一切の物的被害を出していない――と、されている。
それが科学的にどのような現象なのか、あるいは本当に神の御業によるものなのか、今でも盛んに研究が進められているが、目立った成果はないらしい。真里亞の周囲でも、出現後しばらくはその話で持ち切りだったが、結局「ただそこにある」だけで何も起きないことが分かってくると、話題に上る頻度はめっきり少なくなっていった。
「……」
真里亞にとっても、この異様な空は、今や日常であった。
ただ、朝のこの時――寮の玄関を外に出て、その日に初めて
右目の奥に、鈍い痛みが走る。
世界に、突如として神の剣が現れたその日は。
彼女が、不幸な交通事故で家族を喪った日でも、あった。
「――篝火さん!」
「ひゃ!?」
「なにをボケッとしてんだい!? 早く学校行きなさい!」
「は、はい!」
いつの間にか足を止めてしまっていたらしい。生徒たちが遅刻しないよう「追い出し係」を務める寮母のおばちゃんの大声に思考を遮られ、真里亞は一瞬で我に返った。
「ほらほらほらほら!」と圧力をかけてくる彼女に背中を押され、表通りに歩を進める。そのまま他の寮生たちと共に登校しようとした真里亞だが――ふと、再び立ち止まった。
「んがっ!?」と、寮母が真里亞の背に激突する。
「痛ったぁ……。どうしたんだい!?」
「……あのおばあさん、何か探してます」
落とし物をしたのだろうか。通学路とは反対方向にある自動販売機の前で、人のよさそうな老婆がオロオロと地面を見回している。
嫌な予感を覚えたらしき寮母が眉をしかめる。それは、2年間の付き合いを経て、真里亞が次に言い出すことをよく解っている顔だった。
「ちょっと、話を聞いてきます」
「はあ~~~~~~~~…………!!」
心底脱力したような溜息が寮母の口から漏れる。それは、2年間の付き合いを経て、こう言い出した真里亞はテコでも動かないことをよく解った上での溜息だった。
「好きになさい……。ただし、遅刻は許しませんからね!」
「もちろんです」
厳つい表情で釘を刺す寮母の言葉に、真里亞は自信満々で頷いた。
「だって――“普通”の女子高生は、遅刻なんてしませんから」
■
門番のように校門に立つその少女の腕には、「風紀委員」の腕章が巻かれていた。
「新学期開始から10日目。これで5回目の遅刻ですよ、篝火真里亞」
「こ、こんなはずでは……」
二人の背丈は同じくらいのはずだが、今は真里亞の方が小さく見える。俯いていた顔を上げれば、感情の読めない氷のような眼差しが真里亞の背筋を震え上がらせた。
「ち、遅刻と言ってもたった1分、いえ30秒じゃない。大目に見てくれたりは……」
「……」
「……しないわよね。知ってる」
――氷の風紀委員、赤菱サナ。
校則に違反する生徒を次から次へと取り締まり、いかなる例外も認めない。その徹底した態度から「融通の利かないAIのよう」とも称される目の前のクラスメイトは、遅刻常習犯の真里亞にとっても因縁深い相手である。
「遅刻者名簿を作成します。遅刻の理由を述べてください」
「おばあさんが落とした財布はすぐに見つかったのだけど、それをくわえていたのが迷子の犬だったの。その子を飼い主さんのところに連れて行ったら、今度はその飼い主さんがそこら中に貼った『探しています』の貼り紙をはがすっていうから、それも手伝って――」
「簡潔に」
「寄り道をしてしまいました」
事務的で平坦な声が、かえって威圧感を覚えさせる。真里亞は反射的にそう答え、「人助けをしていた」と言った方が印象よかったかな、と後悔した。
言い直す間もなく、サナが遅刻者名簿に記録をつけていく。その淀みのない手つきをぼんやり眺めていると、甲高く、妙に粘っこい声が聞こえてきた。
「なんだ篝火ィ、まァた遅刻か?」
見ると、ぎょろりと突き出した眼球が蛇のように真里亞に向けられている。スーツをかっちりと着込んだ男――生徒を小馬鹿にしたようなその態度を見て、真里亞はぴくりと身を強張らせた。
「……
「困るんだよなァ……。お前、もう三年だろ? こう遅刻ばっかじゃ受験にも響くよ? 僕の評価も落ちちゃうしさァ、頼むよ」
「すみません……」
「お前が遅刻すると、寮母さんの評価も下がるんだよ? いや、別に給料が変わるわけじゃないけどさァ……」
もっとも、遅刻が事実である以上、今の真里亞は反論できる立場ではない。嵐が過ぎ去るのを待つように、彼女はじっと「気をつけ」をしてカラタチの言葉に耐えていた。
「どうしてこんな不良に育っちゃったかねェ……。うちの教育は問題ないと思うんだけど……。あ、やっぱアレかな、
「……!」
それでも、限度というものがある。
何気ない口ぶりから察するに、悪意をもって放った言葉ではないのだろう。しかし、それがかえって胸を抉った。さすがに黙ってはいられず、真里亞は顔を上げる。
と、その時――「風紀委員」の腕章が、二人の間に割って入ってきた。
「先生、言いすぎです。撤回を求めます」
元々大きなカラタチの目が、ギョッと見開かれた。
事務的で平坦な声が、かえって威圧感を覚えさせる。感情の読み取れない瞳で静かに自分を見つめる氷の眼差しを浴びて、彼は己の失言に気付いたようだった。
「あ、あー……。そうだな。すまん、篝火」
「い、いえ」
「まァ、アレだ。とにかく明日からは気を付けるように!」
そう言って、カラタチは逃げるように校舎に戻っていった。
不快な緊張感から解き放たれ、真里亞は胸を撫で下ろす。そして、「ありがとう」とサナに礼を告げた。
「……」
「……あの、サナ?」
サナは何も答えず、感情の読み取れない瞳でじっと見つめてくる。何か言いたいことがあるのかと真里亞が落ち着かずにいると、ぽつりと、サナが言う。
「――『普通の人間でありなさい』」
「……!」
それは――亡き祖母から繰り返し言われ続けた、真里亞の座右の銘であった。
「以前、遅刻をしてまで人助けをする理由を尋ねた時に、あなたはそう言いましたね。普通の人間は、困っている人を放っておかないものだ、と」
「……覚えてたの?」
「人助けは、この社会の秩序を保つために有益な行為です。一方で遅刻は、この学校の秩序を乱す行為でもあります。『普通の人間』を自称するのであれば、両者のバランスを考慮し、一般的といえる範囲まで調整してください」
「調整って……」
眼前の堅物の口から放たれたとは思えない言葉に、真里亞は苦笑してしまった。「氷の風紀委員」と呼ばれてこそいるが、入学してから2年もの間、彼女と相対して遅刻をめぐる丁々発止を繰り広げてきた真里亞には真里亞の言い分がある。
「サナ。あなた自身はそういう柔軟なの苦手でしょう。それを他人に求めるの?」
「……あなたならできると信じています」
ふいっと、「氷」の眼差しが逸れる。自分を棚に上げたその一言に、真里亞は思わず「あ、ずるい」と口を尖らせた。
それとほぼ時を同じくして、朝礼終了のチャイムが鳴る。
「自分の仕事はここまで」と言わんばかりにサッと踵を返し、サナが校舎に向かって歩き出す。鮮やかな撤収に驚きつつも、真里亞は彼女の後を追った。
「こら。まだ話は終わってないわよ」
真里亞の胸によぎるのは――カラタチの言う通り、遅刻がかさむと受験が危ないかもとか、こうしてサナとやり合うのも今年で最後になるのかな、といった――ひどく日常的な思いだった。
まだ何も知らずにいる、真里亞の隣で。
サナが髪に纏った赤い菱形の髪飾りが、鈍く輝いていた。
(つづく)