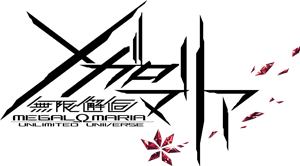昼休みに話しかけてきたのは、意外な人物だった。
「あ、あのっ、真里亞ちゃん……!」
「スミレ?」
垂木スミレ。高校一年の頃から親しくしている、真里亞のクラスメイトである。
「そ、その、お昼……一緒にどう、かな?」
一回り背の低いくりっとした両目がおどおどとこちらを見上げている。その態度は久しぶりに見る
「え? ええ、もちろん」
「あれ、お前ら喧嘩してたんじゃなかったの?」
どこかぎこちなく会話をしていると、近くで弁当を広げていた男子グループが声をかけてきた。「仲直りしたんじゃね?」「最近全然つるんでなかったもんな、あの三人組」と勝手なことを言い合う彼らに向けて、真里亞は深い溜息をつく。
彼らの言う通り、真里亞はここ一週間ほど
「スミレが貸した漫画本の帯をランが紛失した」という、ありがちなきっかけで始まったその事件は――積もるものもあったのだろう、予想以上にこじれてしまった。笑顔がトレードマークのランに至っては、昨日から欠席を続けている。
「……ホッとしたわ。話しかけてくれて」
自分の机に弁当を広げながら、真里亞は苦笑した。
「今週のスミレ、明らかにおかしかったもの。『スタミナを無駄にしたくない』とか何とか言って、ずっとスマホでゲームやってて……。目も血走ってたし」
「ご、ごめんね……。もう、アンインストールした、から……」
そう言って、スミレはスマートフォンを取り出した。そこには、真里亞と出会う前、中学時代にランと撮ったプリクラが貼られている。
「ゲ、ゲームに逃げ込んでたのかな……。今朝起きたらね、ずっともやもやしてた気持ちがスッキリしてて、なんであんなにハマってたのか分かんなくなっちゃって……」
俯きがちにその写真を見つめながら、スミレはか細い声で言う。
「そ、それで……それでね、真里亞ちゃん、もしよかったら……」
「――放課後」
勇気を振り絞り、しかし言い淀んでしまった彼女の言葉を引き取って、真里亞は微笑んだ。
「ランの家に、お見舞いに行きましょうか」
「……うん!」
ホッとしたようにはにかむスミレの笑顔を見て、真里亞も大きく胸を撫で下ろした。
真里亞にとってもスミレとランの仲違いは他人事ではなかった。それは、単に親友だからというだけでなく、
右目の奥に、鈍い痛みが走る。
大切な人は、いついなくなるか分からない。だから。
『――仲直りは、ちょっとでも早い方がいいよね』
不意に聞こえた幼い声に、真里亞は顔を上げた。
「……スミレ? 何か言った?」
「えっ? な、何も……」
じゃあ誰が、と首を傾げ、辺りを見回す。――再び、右目の奥が疼いた。
『廊下。いるよ、もうひとりのクランケさん』
声の出所に疑問を覚えながらも、つられて廊下を見る。
と、
「え……!?」
真里亞と目が合った
■
「――ラン!」
道中は諦める他ないが、ここがひとけのない場所でよかったと、真里亞は思う。なぜなら、もう一人の親友――根本ランは――誰の目にも異様な格好で学校に来ていたからだ。
「どうしたの、その格好……? もしかして、パジャマなんじゃ……」
「……」
ランはぞっとするほど血走った目で真里亞を一瞥すると、何も答えずに出口へと歩き出した。見れば、足元には何も履いておらず裸足である。明らかに正気とは思えないその様子に慄然としながらも、「待って!」と、彼女の肩を掴んで止めようとした時、
――ぐるり、と景色が一回転した。
「うぐっ!?」
次いで、後頭部に鮮烈な痛みが襲い来る。自分が
「ぐ、う……! ラン……!?」
「壊す……」
「……!?」
「壊す、壊す、壊ス、コワす、コワス……!!」
「ラ、ン……! どうした、の……!? 放し、て……っ!」
機械音声のように、感情を喪った声。
その響きに本能的な恐怖を覚えた真里亞は、ランを引き剥がそうともがく。まともな呼吸を奪われた体を死に物狂いで動かし、彼女の下から抜け出そうとして――気付いた。
獣のように血走った、ランの目尻。
「こわす、こわ……す……!!」
そこに、大粒の涙が浮かんでいる。
「ラン……」
本当の彼女が「助けて」と叫んでいる。真里亞には、そう思えた。
それは、都合の良い想像だったのだろう。
「大丈夫、よ、ラン……。私が、助けるから……」
それでも――真里亞は、彼女の背中に両手を回し、優しく抱きしめた。
「う、あ……」
首を締め上げる両手の力が、弱まる。
ランの目尻から涙が零れ、ぴちゃり、と真里亞の頬を濡らす。一瞬、その瞳に正気の光が宿り、その口が何かを言おうと開きかけ――しかし、そこまでだった。
「…………あ…………」
突如として彼女の表情が安らかなものに変わり、そのまま意識を失って崩れ落ちてくる。
気管が一気に解放され、真里亞は激しく咳込む。何が起きたのか分からず混乱しながらも肺を落ち着かせた彼女の視界に映ったのは、若い男だった。
「だ、大丈夫かい、篝火くん。危ないところだったね……」
「立浪、先生……?」
立浪薫。心理カウンセラーとして生徒相談室に配属されている臨時教諭である。茶に染めた長髪を後ろでまとめ、ワイシャツの第一ボタンを開けて首元のアクセサリーを覗かせる教師らしからぬスタイルは気さくで相談しやすいと生徒の間で評判だ。
「びっくりしたよ……。予約の時間になっても来ない根本くんを探してたら、君が首を絞められてるんだから。しかも根本くん、こんな格好だし……」
「ランに、何をしたんですか……?」
「あ、うん。これをね」
言われるままにランの首筋を見ると、そこには小さな湿布のようなものが貼ってあった。「これは?」と尋ねると、タツナミはあいまいに笑って答える。
「鎮静剤……いや、ニコチンパッチみたいなものだよ。興奮を落ち着かせる、ね」
そんな薬は聞いたことがない。真里亞が怪訝な顔をしていると、タツナミは真剣な表情で「これが効いたってことは、やっぱり……」と独り言ち、ランを優しく抱え上げた。
「とにかく、根本くんは家まで送っていくよ。ここからは専門家の出番だ」
「専門家って……!」
食い下がろうとした真里亞を、タツナミは「ごめんね」とすまなそうに押し止める。
「カウンセラーとして、これ以上は話せないんだ。たとえ君が親友であってもね」
「……そう、ですか」
「君も、何かあったら相談に来てね」
結局、真里亞は連れられて行くランを見送ることしかできなかった。
様々な疑問が頭の中を駆け巡る。彼女がうわごとのように呟いていた「壊す」という言葉の意味。彼女が泣いていたわけ。ランの豹変に心当たりがありそうなタツナミの態度。
何か、普通ではないことが起こっている。普通な彼女には、理解もできない何かが。
『悔しい? お姉ちゃん』
声が聴こえる。無力感に苛まれる彼女をからかうような、無邪気な声が。
『なら、お姉ちゃんも壊しちゃえばいいのに。あたし、ずっと待ってるんだよ?』
声が聴こえる。友人のことが知りたいという彼女の欲望を煽るような、蠱惑の声が。
「あなた、は……」
「――篝火真里亞」
氷のような声に呼ばれて、真里亞は我に返った。見れば、目の前に「風紀委員」の腕章をつけた鉄面皮が立っている。
「え、え!? サナ、いつの間に……!?」
「……」
サナの視線は、真里亞の右目に注がれている。何かを考えているらしく、呼びかけるだけ呼びかけておいて何も言わない。無言の時間に真里亞が居心地の悪さを感じ始めた頃、サナは短い溜息をついて、言った。
「――今夜。寮の門限後、垂木スミレの家の前に」
「え……?」
「知りたいのでしょう? 根本ランの異変、その正体を」
「知ってるの!?」
思わぬ一言に、真里亞は声をあげる。対照的に、サナは淡々と続けた。
「立浪先生が作成した根本ランのカルテを読みましたので」
「カルテって、どうやって」
「私は、この学校のあらゆる教室に侵入可能な鍵を複製してあります」
「は?」
斜め上からの答えだった。真里亞は呆れた目でサナを見る。
「いやそれ犯罪じゃない……? あなたの大切な秩序はどこへ行ったの?」
「より広範な秩序維持のためやむを得ないと判断しました。篝火真里亞、垂木スミレ、根本ラン。あなたたち三人の仲が元通りになることによって、クラス内の雰囲気が向上するばかりか、傷心に付け込もうとする不埒な者の数を大幅に減らすことが――」
「……ふふ。もういいわ」
鈍感な真里亞にすら明らかな言い訳に、思わず顔が綻ぶ。少し意地悪かな、と思いつつも、真里亞はサナの本心をズバリと指摘することにした。
「要するに――心配してくれてるんでしょ。私たちのこと」
■
久しぶりに歩く夜の街は、煌々とした満月に照らされていた。
普通の学生である真里亞は、基本的に寮の門限を過ぎて外出することはしない。行き先が閑静な住宅街となればなおさらで、彼女は興味深げに辺りの様子を見回していた。
「不審な動きはしないでください。目的を果たす前に警察に通報されてしまいます」
「……私、そこまで変な動きはしてないと思うけど」
“垂木”と書かれた家の前で、真里亞はサナと合流した。二階建ての一軒家。何度か遊びに行ったことがあるスミレの部屋の電気は、もう消えている。
結局、ランのお見舞いは延期した。ありのままを伝えるわけにもいかず、適当な理由をでっちあげたが、スミレは納得してくれただろうか。
「……『フィトフィリア』」
「え?」
真里亞が親友のことを慮っていると、サナがぽつりと呟いた。
「精神的ショックをきっかけに発症する新種の精神疾患です。幻聴、幻覚、強烈な不安感に苛まれ、その解消のため、特定の事物に依存するようになります」
初めて聞く病名だった。サナの話しぶりも相まって、胸がざわつく。
「依存先は様々です。飲酒、喫煙、ギャンブル。従来から依存症の対象とされてきた事物はもとより、特定の人物に身も心も委ねる、特定の音楽を聴き続ける、そして、特定のゲームに没頭することもある、と言われています」
「ゲーム!? じゃあ、ランだけじゃなくて……」
「そう、垂木スミレ、根本ランが罹患したのは、この病気(フィトフィリア)で間違いありません。親しい友人との仲違いがきっかけで、二人同時に罹患してしまったのでしょう」
「病気、だったのね……」
「『専門家の出番だ』という、立浪先生の言葉の意味が分かりましたか」
真里亞は頷き、ほっと胸を撫で下ろした。
病気と言われた後の反応にしてはおかしいのかもしれない。だが、あの優しいスミレが、あの快活なランが別人のようにおかしくなった原因が「病気」でよかった、と思う。
――カツ、カツと。何者かが、路地を歩いてくる音が聞こえる。
サナの様子からして、他人には聞かせたくない話なのだろう。真里亞は声を潜め、「二つ、訊いてもいい?」と言った。
「どうぞ」
「それを私に伝えるだけなら、どうしてわざわざ夜に、それもこんな場所に呼び出したの?」
「……」
「それと――」
カツ、カツと。
何者かが、こちらに近付いてくる。
「――スミレは、どうやって治ったの?」
真里亞はさらに声を潜めて、サナを見た。
カツ、カツと。
歩いてきた足音が、止まった。
「……時間がないようなので、先に一つ目の質問に答えましょう」
サナが足音の主を見る。真里亞もつられて視線を追って――あっ、と息を呑んだ。
「症状が進行すると、患者はある共通した行動を取ることが分かっています。家族、恋人、親友……。その人がその人であるための居場所を、“壊しに”行くということが」
根本ラン。
そこにいたのは、真里亞がいま一番心配している、もう一人の親友だった。
「貴方をここに呼び出した
「で、でも、あの姿……」
真里亞の声が震える。
街灯の直下で足を止めた親友は、相も変わらず寝間着姿で、一本の糸で吊られた操り人形のように、気だるげに立っていた。表情筋そのものが消え失せたかのように口元は力なく、何も見えてないかのようなその目は、どこにも視点が合っていない。
「あれが、ラン……? 本当に……!?」
「――正確には、彼女はすでに根本ランではありません。根本ランの身体を乗っ取り、根本ランの姿をした、全く別の存在です」
「ア、アア……アアア……!!」
サナの言葉に反応するかのように、ランが自分の顔を押さえて悶え始める。
それは、凄まじい痛みに耐えるかのような、呻き声。
「ア、アアアアアアアアアアアアアアアアアーーーーーーッ!!!!」
そうして始まった“異変”を前に、真里亞は言葉を失った。
絶叫と共に、ランの身体が変質していく。人体が、人体を成しているあらゆる原理原則を無視して捻じ曲がり、折れ曲がり、異形へと姿を変えていく。
ランの素顔が仮面に覆われ、石灰質に似たフード状の外殻がそれを包む。両腕には近寄るものを拒絶するかのごとき逆刃。鈍く輝く二本の鎌を猫背に構えるその怪人は――「死神の尖兵」と表現するのがふさわしい姿だった。
「フィトフィリア患者の成れの果て。心の闇が結実した怪人――アナザー。その“シーカー”タイプ。それが、現在の“根本ラン”の正体です」
「成れの、果てって……」
変わり果てた親友の姿を前に、真里亞は何も言うことができなかった。
「……二つ目の質問に回答します」
立ち尽くす真里亞を尻目に、サナが一歩、進み出る。
「アナザーに乗っ取られた人間を助ける方法は一つだけ。その者の『個』を消し去っている『仮面』を破壊し、あのアナザーに、死を届ければいい」
「死……!? 何を、言って――」
「――言ったはずです。『専門家の出番だ』と」
サナが、制服のスカートを摘まみ上げる。
露わになった左の太腿に――奇妙な刻印が刻まれているのを、真里亞は見た。
「――照覧せよ、
クリスタルの、花。
サナの太腿の刻印から現れた
直後、その花が激しく砕け、眩い光の
「な、なにが……?」
「空間を、元の世界から隔絶させました」
「いや、何を言って……っ!?」
理解させる気のない説明を咎めるようにサナを見て、真里亞は言葉を失う。
「これは、
サナの背後に――赤き異形が、降臨していた。
「……篝火
機械の巫女、と形容すればいいのだろうか。
緋袴の如き紅の肢体はサナよりも少し小柄だが、その場を、
「頭が高い」
「な……!?」
「そなたの友人のため、このアイスアイゼンが力を振るうのじゃ。跪き、頭を垂れよ」
「アイス……アイゼン……」
紅といっても、その体は燃える炎の赤ではない。冷たく、無機的な真紅。
それは、よく知る
この赤き異形は、サナの一部が形になったモノだ、と。
「グギャアァッ!!」
「!」
「……は!?」
瞬間移動したように見えるのは、恐らく、シーカーの動きが人間の認知領域を超えているからだろう。一振りで真里亞の命を刈り取らんとした異形の鎌は――しかし、振り下ろされることはなかった。
「グ……ギ……!?」
「躾がなっておらぬな。わらわの前を素通りとは」
シーカーに向けて、アイスアイゼンが片手を突き出している。それだけで、シーカーは身動きが取れなくなっていた。まるで、全身を糸で縛られたかのように。
と、耳をつんざくような銃声が響き、シーカーが吹き飛ばされる。
「言った通りでしょう。あれは垂木スミレを、そしてあなたを狙う。自分が自分であるために重要な居場所、親友(・・)を壊すために」
「サナ……!?」
「何か?」
「いや、それ銃……。というか、その格好は……!?」
サナの衣服は、黒みがかった赤を基調とする軍服風のドレスに変化していた。その一部にゴシック・ファッションを彷彿させる意匠が施されながらもタイトなハーネスが布を締め付けており、動きやすそうな印象を与えている。彼女の細腕の先で白煙を上げている拳銃はあまりにも大きく武骨で、人に「死を届ける」ために使うにはあまりに過剰であることは素人の真里亞にも明らかだった。
「ギ、ギ……」
「……やはり、この程度では威力不足ですか」
だが――その直撃を受けた
「いつもの銃はないのか?」
「あれは隠密専用です。私の姿を見られている以上、命中するとは思えませんが」
「何を他人事のように……。そこの某に説明するためだからと、あえて姿を晒す判断をしたのは――サナ、お主自身じゃろう」
言い合いながら、アイスアイゼンは巫術のような力で、サナは銃撃で、交互に連携してシーカーの足を止めている。高慢なアイスアイゼンがサナに呆れるという微笑ましいやり取りに混じって響く殺人的な銃声に、真里亞は混乱していた。
この世界は、どこまでも「普通」の世界ではなかったか。
この自分は、どこまでも「普通」の人間ではなかったか。
真里亞が思い描く「普通の女子高生の生活」には銃も怪人も存在しない。ましてや、その怪人が自分の親友で、しかも自分の命を狙ってくるなど――現実感がないにも程がある。
全てに目を背け、今すぐここから逃げ出せば、なかったことにできるだろうか。
明日の朝、寮のベッドで目覚めれば、いつも通りの日常が戻ってくるだろうか。
「普通の人間でありなさい」という、祖母の言いつけどおりに。
「……違う」
それでも、それが自分にとっての「普通」ではないことくらい、真里亞は分かっていた。
世界とか、怪人とか、今はそんなことはどうでもいい。「普通」の人間として、「普通」の女子高生として、今、自分がやるべきことは一つしかないはずだ。
「サナ」
迷いのない目で、隣に立つ友人を見る。
「私も手伝うわ。どうすれば、ランを助けられるの?」
そんな真里亞の言葉に、赤い菱形の髪飾りをつけた少女が――驚いた、気がした。
「……なるほど。お主が目をかけるのも分かるのう」
愉快そうに言葉を弾ませ、アイスアイゼンが大きく腕を振るう。シーカーではなく、その背後に建つ住宅を狙って空間を湾曲させると、ぐにゃりと捻じれた建物が強度の臨界点に達し、一気に崩壊した。
「ギギッ……!?」
降り注ぐ瓦礫がシーカーを生き埋めにする。それを見届けたサナは銃を下ろし、相変わらずの鉄面皮で真里亞へと向き直った。
「その言葉だけで十分です、篝火真里亞」
「わらわたちにはもう一つの……否、星の数ほどの武器がある」と、アイスアイゼンも真里亞を見る。「
「は? は?」
この人たちは、何を勝手に納得しているのだろうか。
一方的な感想だけを真里亞に押し付けて、サナは手にしていた銃をホルスターに収めると、自分の胸元に両手を重ねて置く。
そして、もう一度だけ真里亞を一瞥し――フッと、微笑んだ。
「――セキュリティ・クリアランス“レッド”。クラウドゲート開放」
風が、巻き起こる。
アイスアイゼンの体のスロットから破魔の札が次々と飛び出し、渦を巻いて上空へと舞い上がる。破魔札は天高く六芒星の形に静止し――その中央に、「門」が開いた。
「アーカイブデータにアクセス。
CALL――『勇ましき英雄たちよ。私には貴方たちが必要です』」
赤い菱形の髪飾りが眩い光を放ち、サナの全身を包み込む。と、その求めに応えるかのように、「門」が淡く輝き始めた。
魔術の輝きではない。よく見れば、「門」の内側に無数のプログラム・コードの光が駆け巡っている。コードは「門」の中心に向けて続々と集まり、互いに絡み合い、螺旋状に膨れ上がりながら、一つの光の塊になっていく。
「アイスアイゼン」
「わらわが人前で戦うのじゃ。馬を回せ」
サナが問い、アイスアイゼンが答える。吹き荒れる風の中、その意図を汲んだらしきサナが、厳かに告げた。
「赤の女王、SANATが命ずる。
「門」に収束していた光の塊が、アイスアイゼンに降り注いだ。
コードが実行され、見慣れぬ金属でできた「機獣」が徐々に実体化していく。剛とした四つ足、一角獣と見紛う鋭利な角。機体各所に配された六角孔が、この機獣の出自を、どこか異なる世界の技術であることを、雄弁に物語っている。
高らかに
「Combat preparation complete. Start your engines.」
サナが、最後の命令を下す。
と、アイスアイゼンの両足がふわりと大地を離れ、戦場を俯瞰するかのように上空に浮き上がった。
「――駆けよ、ジーク・スプリンガー」
鉄騎が、大地を蹴った。
瓦礫から身を起こしたシーカーが、猛然と迫り来る赤馬を迎撃する。
目にも留まらぬ、死神の鎌の一薙ぎ。しかし、上空のアイスアイゼンが――まるで手綱を引くかのように――腕を動かすと、ジーク・スプリンガーが、跳躍した。
そのままシーカーを飛び越え、半身になりつつ前足から着地する。背後を取られたシーカーが振り向くより早く――鉄騎が誇る赤き一本角が、その体を薙ぎ払った。
「ガ……アッ!?」
疾さと、重さ。二つを兼ね備えた一撃が、シーカーを壁に叩きつける。
「すごい……」
真里亞の口から零れ出たのは、あまりに凡庸な言葉だった。
無理もないことだ。「門」の解放、「機獣」の召喚、それを操るアイスアイゼンの戦い。立て続けに起こった一連の現象を表現する語彙を、彼女は持っていなかった。
「あれがアイスアイゼンの本来の能力です。自らの身体を依代として、
「不完全?」
意味深な単語に反応して、真里亞はサナを見る。だが、サナは視線を返さなかった。
「よく見ておきなさい、篝火真里亞。アナザーの戦いというものを」
緩、そして急。
アイスアイゼンの指示に従い、あたかも生き馬のように四つ足を動かして死角に回り込み続けるジーク・スプリンガーの挙動を嫌ったのか、シーカーが大きく飛び退いて距離を取る。そして、深く腰を落として力を溜めると、矢のように斬りかかった。
ギイィン、と、金属がぶつかり合う音が響く。
――死神の鎌を防いだのは、赤馬の一本角だった。
「……哀れな単細胞よ。その一撃を誘ったのが分からぬか」
文字通り――上空からシーカーを
「ギ、ギッ……!?」
「はいやっ!」
大きく背を仰け反らせ、ジーク・スプリンガーが前足を持ち上げた。
野生の膂力。一本角で突き上げられたシーカーの体が、空中に吹き飛んだ。
「では、“
アイスアイゼンが、その腕を高らかに振り上げる。
「――はっ!」
掛け声と共に、ジーク・スプリンガーが疾駆した。
尾のように畳んでいたテール・スラスターを展開し、一気にバーナーを噴かす。赤馬はほんの僅かな時間で最高速に到達すると――その一本角が、落下してくるシーカーの仮面に、狙いを定めた。
瞬間、一本角が赤熱する。
あらゆるものを溶断する超高温の斬撃――
「はあああああっ!!」
宵闇の中、まるで流星のように輝白色の軌跡を残して、ジーク・スプリンガーがシーカーと交錯する。直後、親友の顔を隠していた死神の仮面に横一文字の亀裂が走り――真っ二つに、割れた。
「……ラン!」
もんどりうって地面に叩きつけられた怪人に駆け寄って、その上半身を抱き起こす。視界の端で、役目を終えたジーク・スプリンガーが再びデータの光に戻っていくのが見えたが、真里亞にとってそんなことは二の次だった。
仮面に次いで、
「これが、敵に死を届けるということ。フィトフィリアの治療は、これで完了です」
気付けば、サナが近くで見守ってくれていた。彼女が作り出していた隔絶空間が解除され、世界に音が戻ってくる。全てが終わった安堵感からか、閑静な住宅街でも、意識してみるとそこかしこに人間の生活音がするものだな、と真里亞は見当違いのことを思った。
「アナザーに乗っ取られている間の記憶は、当人には残りません。明日には、いつも通りの根本ランに戻っているはずです」
「よかった……」
「専門家」の太鼓判に、真里亞は大きな溜息をついた。
色々と訊きたいことはある。ランのこと、スミレのこと、そして何よりサナのこと。初めて聞く病気、初めて見る光景――しかし、それは明日でいい。あまりにも多くのことが起こりすぎて、今から説明されても全く頭に入る気がしない。
明日、ランとスミレの仲直りを見届けたら、サナを呼び出して問い詰めてやろう。たまには早めに登校して、門番の仕事を手伝いながら話を聞くのもいいかもしれない。
そう、緩みきった頭で考えていた時だった。
――ずぐり、ぶちぶちぶち、と。
何か、切れてはいけないものが切れる音と共に、頬に生暖かいものが付着した。
「え?」
顔を上げる。
目に入ったのは、鮮血。そして、それを滴らせている異形の手、だった。
「…………サ、ナ?」
その、手刀は。
今し方まで話していた友人の体を――刺し貫いていた。
(つづく)